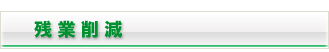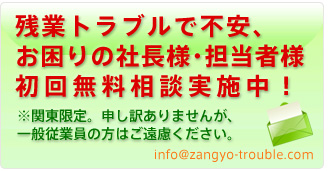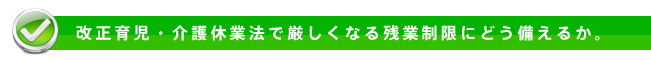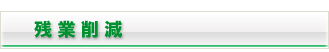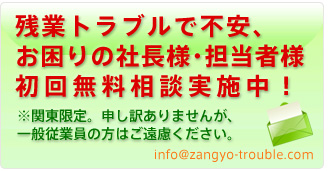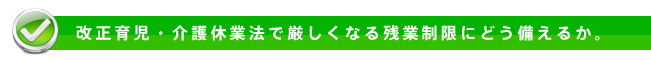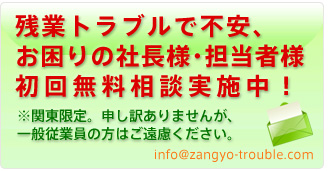
東京人事労務ファクトリー
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-13-5 BPRレジデンス渋谷1002
TEL : 03-5778-9817
(平日9:00~18:00)
※スマホの場合、電話番号をタッチすると
電話が掛かります
事務所のご案内はこちら |
|
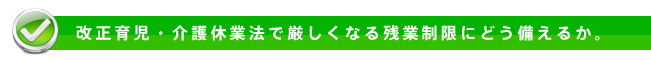
Q.
当社では女性社員の比率が高く、育児休業後も子育てと仕事を両立する社員に対しては育児・介護休業法にも定めのある、始業・終業時刻を本人の希望により繰り上げ、または繰り下げる措置をとってきました。
ところが、平成24年7月1日からは、従業員が100人以下の当社にも、育児・介護休業法の改正が適用され、勤務時間の短縮と残業を免除する措置が義務化されるということです。
ちょうど現在、これらの措置の対象となる女性社員が多数出ていて、一気に請求されると人員体制が相当厳しくなりそうです。
例外として「事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は労働者からの請求を拒むことができる」ということですが、社内の事情を理由に、短時間勤務制度か残業の免除措置の少なくともどちらか一方の請求を退けることはできないでしょうか?
|
A.
それはなかなか難しいと思います。といいますのも、「事業の正常な運営を妨げる場合」と判断されるためには、相応の根拠が必要だからです。
その社員の勤務時間の短縮や残業の免除により、事業運営に重大な支障をきたすということが、客観的に証明されなくてはなりません。
残念ながら、会社側の都合だけで勤務時間の短縮や残業の免除の請求を拒むことは認められません。
社員側から措置の請求があった場合は、組織としての生産性が低下しないように業務の分担を図り、他の社員も納得のいくように処遇をおこなうことで対処しましょう。
育児を行う社員を活用するためには相手の意見も聴き、フレックスタイム、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、託児施設の設置など、改正前からの措置の実施を併せて検討されることをお勧めします。
|
1.育児と仕事の両立への配慮がさらに求められることに。
① 改正育児・介護休業法のねらい
厚生労働省「平成22年度雇用均等基本調査」によると、働きながら子育てをする女性の83.7%が育児休業を取得し、そのうち7.9%が職場に復帰せず退職してしまうという統計が出ています。
社会全体に「女性は仕事を辞めて育児に専念するべきだ」という固定観念がいまだ根強く残るなか、女性社員が結婚や出産にともない退職するということを前提として、労務管理をおこなっているという会社は少なくありません。
さらに、ここ数年の経済情勢の悪化に伴い、育児休業にかかわる解雇や退職勧奨(いわゆる育休切り)は多くなる傾向にあります。
こうした現状にかんがみて、女性はもちろん、男性も育児をしながら働きやすい環境を整備しようというのが、改正育児・介護休業法のねらいです。
改正育児・介護休業法により新たに会社に課されることになった義務はいくつかありますが、ここでは労働時間に与える影響についてご説明していきましょう。
② 法改正により新たに義務づけられた点
改正前は、1歳未満の子を育てながら出勤する社員については以下の措置のいずれか一つ、1歳以上3歳未満の子供を育てる社員については、以下の措置のいずれか一つ、または育児休業に準ずる制度を実施すればよいとされていました。
・勤務時間の短縮
・所定外労働の免除
・フレックスタイム
・始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ
・託児施設の設置運営
・託児施設に準ずる便宜の供与
それが改正後は、勤務時間の短縮、所定外労働の免除につき、これら両方を実施しなければならないこととなりました。
ただし、必ず実施するということではなく、あくまでも社員本人から請求があった場合に、これに応じて措置をとることが義務づけられることになったということです。
会社としては「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しなくとも、本人と話し合って申請を思いとどまってもらうこともできるわけですが、引き続き勤続してもらい、育児を行う社員のキャリアを活かす観点からすると、得策とはいえません。
2.今から法改正への対応を!
① 中小企業に対する改正育児・介護休業法の適用はこれから
注意しておきたいのは、中小企業に対する改正育児・介護休業法の適用は、これからだという点です。
常時100人以下の従業員を雇用する事業主については、平成24年6月30日まで勤務時間の短縮および所定外労働の免除の義務化は猶予され、同年7月1日から適用となります。
改正法が適用となると、裁量労働制、事業場外のみなし労働時間制、フレックスタイム制などの労働者も所定外労働免除の対象となるので、こちらも注意が必要です。
なお、育児・介護休業法の規定により入社から1年に満たない社員、1年以内に退職する予定の社員、週の勤務が2日以下の社員(アルバイト)などは、労使協定により育児休業自体の適用を除外することが可能となりますので、当然その場合は勤務時間の短縮、所定外労働の免除および改正前の措置の対象とはなりません。
② 従来からの措置も確認しておく
3歳未満の子供を育てる社員への措置に比べると忘れられがちですが、小学校入学前の子を養育する社員におこなわせる法定時間外労働の制限は、今までと変わらず義務となっています。
すなわち、対象者から請求があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月につき24時間、1年につき150時間を超える法定時間外労働をさせてはいけません。
また、妊産婦が休業せず出勤する際に請求があった場合には、法定時間外労働、深夜業(午後10時~午前5時)、休日労働のいずれもさせてはいけないという点も、従来と変わりありません。
ただし、日々雇用される者、継続して雇用された期間が1年未満の社員、1週間の所定労働日数が2日以下の社員(アルバイト)はこれらの請求ができません。
改正前はこの他に、「配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる者」が請求をできないことになっていましたが、改正後は請求ができるようになりました。
つまり、妻が専業主婦である男性社員でも、「イクメン」という言葉が聞かれるとおりに育児休業の請求ができるようになったのです。
夫が妻の休業に続けて休業を取れるようになったことと併せ、夫婦で力を合わせ育児と仕事を両立しやすい環境となったわけですが、その分会社は配慮をおこなう必要が新たに出てきたといえます。
まだ改正育児・介護休業法の適用となっていない中小企業では、今から就業規則などを法改正に対応させる準備をおこないましょう。
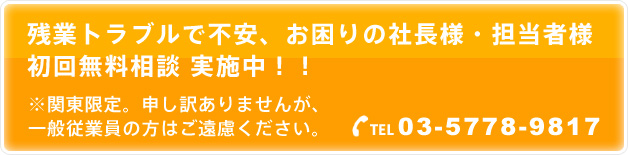
|
|